1. 表色系とは?
表色系(ひょうしょくけい)とは、色を数値的に表現する方法や基準のことです。私たちは普段、色を「赤」「青」「緑」と言葉で認識しますが、機械やコンピューターは色を数値で扱います。そこで、どのように数値化するかを決めたのが 表色系 です。
具体的には、色を表すために「明るさ(輝度や反射率)」や「色味(色相、彩度)」などを数値化し、色を座標上にマッピングします。
これにより、異なる機器や環境間でも「同じ色」を再現・比較しやすくなります。
2. 表色系と色空間とは?
初心者にとって「表色系」と「色空間」は似たように聞こえますが、実は意味が少し異なります。両者の違いと関係を理解することで、色管理の基礎知識がより明確になります。
表色系(Color System)とは?
表色系は、色を数値で表現するための方法や原理のことを指します。つまり、色をどのように記述し、分類するかのルールやモデルのことです。
- CIE Lab表色系は「色をL*(明度)、a*(赤緑軸)、b*(黄青軸)の3軸で表現する」という原理・方法。
- マンセル表色系は「色相、明度、彩度で色を表す」という体系。
色空間(Color Space)とは?
色空間は、表色系の原理を具体的に数値化し、三次元や二次元の座標空間として定義したものです。
色空間は、表色系のルールに基づき、実際に色の数値範囲や色域(表現可能な色の範囲)を定めたものと言えます。

| 用語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 表色系 | 色を表すためのモデルや原理、方法論 | CIE LAB、マンセル表色系、CIE XYZなど |
| 色空間 | 表色系の原理を数値的に実装した座標系 | Yxy色空間、L*a*b*色空間 |
色空間について、詳細の情報をお求める方は以下のブログよりご参照ください。
色空間/カラースペースの定義と種類を徹底解説
3. なぜ表色系が必要なのか?色管理における役割
製造や印刷業界で色の管理が重要な理由は、
- 商品の品質を一定に保つため
- ブランドイメージを正確に伝えるため
- 顧客の期待に応えるため
たとえば、ある企業のロゴが特定の赤色であった場合、その赤色が印刷物や製品でバラバラに見えたらブランド価値が損なわれます。そこで、数値で色を指定し、誰でも同じ色を再現できるようにすることが必要です。このとき使われるのが 表色系です。
表色系があることで、
- 色の再現性を検証できる
- 複数の機器間で色の整合性を取れる などのメリットがあります。
さらに、
- 色の差を数値で比較しやすい表色系が選ばれる
4. IEとは?国際照明委員会の色規格の重要性
CIE(Commission Internationale de l'Éclairage)は、国際照明委員会という機関で、色や光に関する国際的な標準を制定しています。現在、最も信頼されている色の表現基準はこのCIEによって作られたものが多く、さまざまな表色系の基盤となっています。
代表例は以下の通りです。
- CIE XYZ 表色系(1931年)
- CIE LAB 表色系(1976年)
- CIE LUV 表色系(1976年)
5. 代表的な表色系の種類と特徴
5-1. CIE XYZ表色系/Yxy色空間
XYZ表色系は、1931年に国際照明委員会(CIE)によって制定された表色系の一つです。このシステムは、色を三次元の座標で表現することで、色の数値化を可能にします。XYZ表色系では、色をX、Y、Zの三つの成分で表し、各成分が異なる色の特性を持っています。
XYZ表色系の最大の特徴は、色知覚を数値化したことにあります。色彩の科学的分析や研究において、広く利用されています。
また、XYZ表色系は他の表色系との変換基盤としても機能するため、例えばマンセル表色系やRGB、CMYKといった異なる形式の色を変換することが容易です。これにより、デザインや印刷、映像制作など、さまざまな分野での応用が進んでいます。
- 概要:CIEが1931年に定めた最初の標準表色系
- 特徴:人間の目の3つの錐体細胞(L、M、S)による感度を数学的にモデル化し、X、Y、Zの3つの値で色を表す。
- 用途:他の色空間の基準として使われる。実際の色再現には不向きで、単独ではあまり使われない。
- ポイント:Y成分が明るさ(輝度や反射率・透過率)を表す。

5-2. CIE LAB 表色系/L*a*b*色空間
CIE LAB表色系は、均等色空間を考慮して開発された表色系の一つです。このシステムは、国際照明委員会(CIE)によって定義されており、視覚的な色の感じ方に基づいた構造を持っています。
L*a*b*色空間は、L*(明度)、a*(赤緑軸)、b*(黄青軸)の三つの成分から成ります。L*は黒から白までの明度を示し、a*は赤から緑の間の色を、b*は黄から青の間の色を示しています。 このため、さまざまな色を細かく表現することができ、特に色の計測や再現において優れた精度を誇ります。
- 概要:ハンターLabを元に均等色空間を考慮した表色系。CIE XYZから計算が可能。
- 特徴:L*(明度)、a*(赤緑軸)、b*(黄青軸)の3成分で色を表す。人間の色感覚に近く、色差計算に適している。
- 用途:印刷、塗装、繊維業界などで色管理の基準として広く使用されている。
- メリット:異なる色の違いを数値的に測定可能。

5-3. CIE LUV表色系/L* u* v*色空間
- 概要:均等色空間を考慮したu’v’座標を反射物体色でも使用できるようにした表色系。
- 特徴:L*(明度)はCIE LABと共通、u*、v*は光源色用のu’、v’と同じ。
- 他の表色系との違い:用途や計算方法が異なり、独自な別の表色系。

5-4. RGB 表色系
- 概要:赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)光の三原色を組み合わせてよく使われる色空間。
- 特徴:ディスプレイやデジタル機器の色表現に一般的なデバイス依存の表色系。
- 用途:パソコンモニター、スマホ画面、テレビなど。
- 注意点:RGBにはsRGB、Adobe RGBなど表示範囲の違う複数の規格があるため、同じRGBでも色が違うことがある。
5-5. マンセル表色系(Munsell Color System)
- 概要:アメリカのアルバート・マンセルが考案した色の分類体系。
- 特徴:色相(Hue)、明度(Value)、彩度(Chroma)の3つの軸で色を表す。
- 用途:色彩教育やデザイン分野で広く使われている。
- ポイント:直感的でわかりやすい色表示が特徴。色の心理的なイメージを捉えやすい。

6. 実務での色管理に役立つ表色系の選び方
印刷/製造現場では CIE LAB を使うことが多い
印刷や塗装の世界では、色の差異を正確に測り、管理することが求められます。そこで使われるのが CIE LAB です。 CIE LABの色差ΔE*ab=ΔE*=ΔE76は、人間の視覚に近い色差計算ができるため、よく使われていたが、現在では同じ色空間上で、より補正した色差ΔE2000=ΔE00が良く使われている。
マンセル表色系は色彩教育やイメージ共有に最適
デザイナーや色彩教育の現場において、色のイメージを伝えるのにマンセル表色系はわかりやすく使われています。
まとめ
- 表色系/色空間は色を数値で表現し、色の管理・再現を可能にする仕組み
- CIEは国際的な色規格の基準を作る組織で、多くの表色系の基盤となっている
- 主要な表色系にはCIE XYZ、CIE LAB、CIE LUV、RGB、マンセルなどがある
- 色管理を正しく行うことで製品の品質向上やブランド価値の維持に貢献できる
色の世界は複雑ですが、まずはこのような代表的な表色系の違いと使いどころを理解することから始めましょう。
おすすめの参考資料
-
カラーコミュニケーションガイド|ホワイトペーパー
本書は色のノウハウを紹介するガイドです。アートやカラーサイエンスの初心者・上級者を問わず、正確な製品色を確保し、ブランドイメージを維持するための、購買意思決定の瞬間を左右する情報を提供します。 -
パッケージング コンバーター向けの色管理|業界別のソリューション
フィードバック式のソリューションは、一貫性と予測性のある色を指定、コミュニケーション、作成、監視します。
関連製品一覧
色と見えの原理:オンライン(FOCA)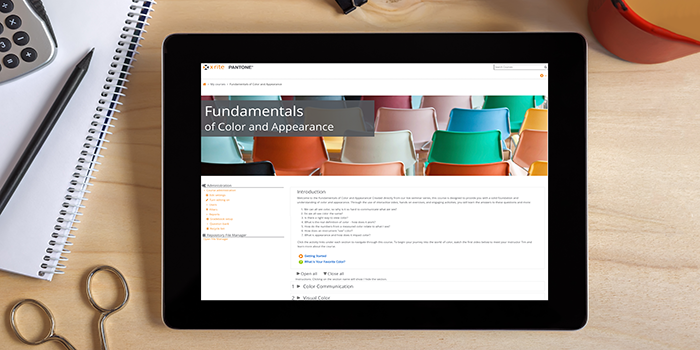
「色と見えの理論」のオンラインコースは色の基礎知識を提供、測色&データの理解や、信頼のおけるカラー品質プログラムとは何かを説明します。 |
ポータブル分光濃度・測色計シリーズ「eXact 2」
ポータブル分光濃度・測色計シリーズ「eXact 2」市場初の特許認定 Mantis™ ビデオターゲティングやデジタル ルーペのズーム技術など、革新的な機能を備えた eXact 2 は、印刷会社、コンバーター、インクサプライヤーに最適な製品です。 |
お問い合わせや、無料相談・無償機材貸出・製品見学会のお申込はこちら
