はじめに
私たちは日常生活の中で無意識に色を認識しています。赤いバラ、青い空、白い紙などです。
しかし、「なぜ色が見えるのか?」と聞かれると、明確に説明できる人は少ないかもしれません。色が見える仕組みは 光・物体・人間の視覚 という3つの要素が関わる現象です。
本記事では、この3つの要素を中心に、初心者でもわかるように色の見え方を解説します。印刷・デザイン・塗装など、「色が見える仕組み」を理解することは、色を扱う仕事をしている方にも役立つ内容です。
1. 色が見えるための3つの要素
色の見え方は、単独の要素で決まるわけではありません。 光源(照明)、物体、人間の目と脳 が相互に作用して初めて色が見えます。
1.1. 光(光源)
色の認識は光から始まります。光は電磁波の一種で、その中でも私たちの目に見える範囲(波長380〜780nm)を 可視光と呼びます。 光にはさまざまな波長が混ざっており、これが色の基礎になります。
- 短波長(約400nm前後)→ 青や紫
- 中波長(約500〜570nm)→ 緑
- 長波長(約600〜700nm)→ 赤やオレンジ
光源によって放出される波長の分布が異なるため、同じ物体でも照明が変わると色が違って見える現象があります。これを**メタメリズム(条件等色)**と呼びます。 例えば、印刷物を蛍光灯下と太陽光下で比べると色味が変わるのは、光源のスペクトルが違うためです。

可視光スペクトルについて、詳細を知りたい方は以下のブログよりご参照ください。
可視光スペクトルとは?
1.2. 物体
物体自体には「色」があるわけではありません。物体の表面は光を 反射・吸収・透過します。私たちが目にしている色は、物体が反射した光の波長によって決まります。
- 赤いリンゴ → 青や緑の波長は吸収し、赤の波長を反射
- 白い紙 → 可視光全体をほぼ均等に反射
- 黒い布 → 可視光をほとんど吸収
この性質は素材や表面構造にも影響されます。光沢面(ピアノの塗装など)は鏡のような反射を起こし、マット面(マット紙や無光沢塗装など)は拡散反射によって柔らかく見えます。
1.3. 人間の目と脳
光が物体で反射され、私たちの目に届くと、網膜にある 錐体細胞と杆体細胞が反応します。
- 錐体細胞(3種類)
- L錐体(長波長、赤系)
- M錐体(中波長、緑系)
- S錐体(短波長、青系)
- 杆体細胞 → 明暗認識(色の認識はほぼなし)
これらの細胞が受け取った情報は視神経を通じて脳に送られ、脳が「色」として認識します。この3種類の錐体細胞の信号が脳で統合されることで、多様な色を知覚できるのです。

2. 光・物体・視覚の関係性
色は光源のスペクトル × 物体の反射特性 × 人間の視覚特性の掛け算で決まります。 どれか一つが変わるだけで、色の見え方も変わります。
- 例:
- 光源が変わる(太陽光→LED照明) → 色味が変化
- 物体の塗料や顔料が変わる → 反射する波長が変化
- 視覚的条件(周辺色の影響、色覚の多様性、疲れ目など) → 認識色が変わる
3. 光源による色の違い
3.1 光源による色の違い
同じ物体でも、光源が変わると色の見え方は変化します。
- 昼間の太陽光:自然でバランスの取れた光。
- 白熱灯:赤みが強調され、暖かい色味に見える。
- 蛍光灯:青や緑が強く見えることがある。
この現象はメタメリズム(条件等色)と呼ばれ、印刷・塗装の現場では重要な課題となります。

3.2 色が変わって見える要因
現場で色を扱う人にとって、色の変化は品質やデザインの問題につながります。主な要因は以下の通りです。
- 照明条件の違い
- 背景色や周囲の色の影響
- 観察者の色覚の個人差
- 観察距離や観察範囲
- 素材の質感や表面処理
例えば、色評価の現場では、昼光・蛍光灯・LEDといった複数の照明環境で確認することが推奨されます。
4. 物体と色の見え方
4.1 反射と吸収
物体は特定の波長を吸収し、残りを反射します。その反射光が私たちの目に届くことで色を感じます。
例:
- 緑の葉 → 緑の光を反射、赤と青を吸収。(実際の緑の葉は赤も反射しています)
- 青い車 → 青の波長を反射、他を吸収。
4.2 表面の質感と色
表面がツヤありかマットかで色の見え方も変わります。光沢面は反射が強く、鮮やかに見えます。マット面は拡散反射が多く、落ち着いた印象を与えます。
5. 色が見える仕組みに関するよくある質問
Q1. 色はどのようにして見えるのですか?
色は、光源のスペクトル(波長の組み合わせ)、物体の反射・吸収特性、そして人間の視覚の3つの要素が組み合わさって見えます。光が物体に当たると特定の波長が反射され、その光が目に入り、脳が「色」として認識します。
Q2. 光が変わると色が違って見えるのはなぜですか?
光源によって含まれる波長の分布(スペクトル)が異なるためです。
例えば、昼光は波長が均等に含まれますが、蛍光灯やLEDは特定の波長が強く、他が弱い場合があります。このため、同じ物体でも照明条件によって色が変わって見えます(メタメリズム現象)。
Q3. 人によって色の見え方が違うことはありますか?
あります。色覚には個人差があり、**色覚の多様性**の一部の人は特定の波長の認識が弱い場合があります。また、年齢や疲労、周囲の光環境によっても色の感じ方が変わります。
Q4. 物体そのものに色があるのですか?
厳密には、物体そのものに色はありません。物体は光を反射・吸収・透過する性質を持っており、その反射した光の波長によって色が決まります。
例えば赤いリンゴは赤の波長を反射し、それ以外を吸収しています。
Q5. 色を正確に管理するにはどうすればいいですか?
肉眼だけでは色の判断が主観的になりやすいため、分光測色計や色差計などの測定機器を使うのが効果的です。
また、観察条件を標準化(例:D65/10度視野、D50/2度視野など)することで環境による色の見え方の差を最小限にできます。
Q6. なぜ印刷や塗装では色の測定が必要なのですか?
製品の色が設計通りか、ロット間でブレがないかを客観的に確認するためです。特にブランドカラーや特殊色は、微妙な差でも顧客の印象や製品価値に影響します。
まとめ
色が見える仕組みは光源・物体・人間の視覚という3つの要素が揃って初めて成立します。 現場での色管理では、この3要素を理解し、測定機器や標準化された照明環境を活用することが、品質維持と効率化の鍵になります。色を正しく理解することは、単に美しさのためだけでなく、製品価値やブランドイメージの保持にもつながります。
おすすめの参考資料
-
カラーコミュニケーションガイド|ホワイトペーパー
本書は色のノウハウを紹介するガイドです。アートやカラーサイエンスの初心者・上級者を問わず、正確な製品色を確保し、ブランドイメージを維持するための、購買意思決定の瞬間を左右する情報を提供します。 -
パッケージング コンバーター向けの色管理|業界別のソリューション
フィードバック式のソリューションは、一貫性と予測性のある色を指定、コミュニケーション、作成、監視します。
関連製品一覧
色と見えの原理:オンライン(FOCA)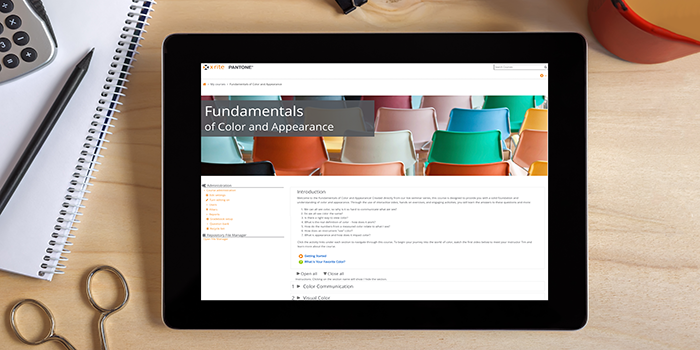
「色と見えの理論」のオンラインコースは色の基礎知識を提供、測色&データの理解や、信頼のおけるカラー品質プログラムとは何かを説明します。 |
標準光源装置 Judge LED
標準光源装置「Judge LED」は多様な照明条件を再現する7つの異なる光源により、正確で一貫性のある色評価を実現します。 |
ポータブル分光濃度・測色計シリーズ「eXact 2」
ポータブル分光濃度・測色計シリーズ「eXact 2」市場初の特許認定 Mantis™ ビデオターゲティングやデジタル ルーペのズーム技術など、革新的な機能を備えた eXact 2 は、印刷会社、コンバーター、インクサプライヤーに最適な製品です。 |
お問い合わせや、無料相談・無償機材貸出・製品見学会のお申込はこちら
